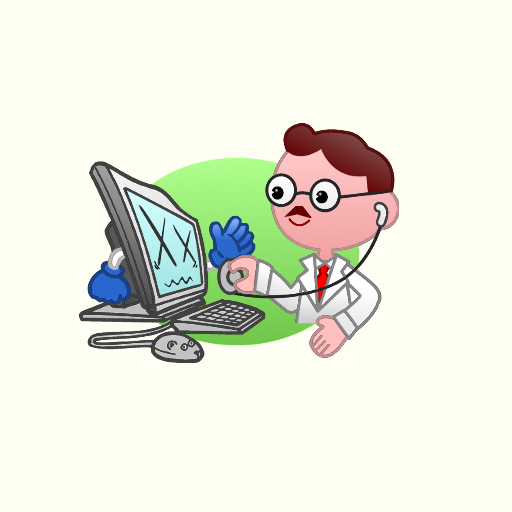年を取ると、老眼鏡が必要になってきた。眼鏡無しに気軽に新聞でも、と試しても字が少しぼやける。近視の軽い人は、年をとると老眼鏡を必要としない場合もある、と聞きかじっていたから運がよければ・・・・と密かに期待していたのに当てが外れた。
検査して買い求めた眼鏡なのに、使ってみてなんと不便な眼鏡なんだろうと思った。老眼鏡は近くはハッキリみえるが、遠くはぼんやりしている。長いすに座って新聞、雑誌をゆっくり読んでいる時は、十分に機能を発揮するが、本を調べ、立ったり、座ったりの作業中は、かけたり、はずしたりでなんとも不便である。その難点を友人に話すと、一つで遠近両方がみえる眼鏡があると教わり試したが、使い慣れるまえに諦めた。どうも使いづらい。近くの物がハッキリする方に重点を置く老眼のレンズのみとし、遠くはぼんやりしても我慢することにした。その老眼鏡、外出用と二つめを買ったのにどこかへ置き忘れ、もう一度買うチャンスをねらっていた。
日本滞在もあと一週間というとき、厄介になっている友達の奥さんから「叔母さんのとこへはもう顔を出したのね」と聞かれた。自転車なら幾らもかからぬ場所なのに、まだ訪ねていなかった。会って久々に話をするのは楽しいが、その後決まってお年玉持って行け、と包んでくれる。子供の頃からの習慣で、あの頃は嬉しかったがこの年になると何故か恥ずかしく逃げていた。
「なに言ってんの、くれると決まったわけでもないのに」と肩を押されるかたちで家をでた。叔父は仕事を辞め、子供たちは夫々独立。夫婦二人でのんびりと暮していた。昔の近所の友達は案外年若くして亡くなり、それが話せるのも叔母くらい。訪ねてよかった、と感じ「次はいつになるかわからんけど、帰るね」と立つと、すかさず「持っていけ」と言われた。やはり照れたが、有難くいただくことにした。眼鏡はこのお金で買おう、叔母の記念の眼鏡になる。買う店は決まっていた。
城下町として栄えたこの街は、お城を中心に碁盤の目のように区分けされ、解り易い街なのに目指す本屋がみつからない。思い余って前から来た女性に声をかけた。知らん顔をされるかな、と思ったが、親切に教えてくれ。「ふうーん、姫路のひとはこころが優しいのだ」と感心した。本屋の帰途、立寄った眼鏡屋、対応してくれたのは今朝方の女性「おや貴方は・・・・」先方も覚えていてニッコリ。チョッと会話も弾み、世の中、数少ない縁を楽しんだ。
購入当日、目の検査、めがね選び、を手伝ってくれたのは若い青年。てきぱきとていねいに対応してくれ、叔母の記念の眼鏡が購入できた。
さあこれでいよいよ帰伯と荷物の整理中、おみやげ用の食材が数点でてきた。だれにあげるか迷った末、眼鏡店の女性と青年を思いだした。翌日でかけると、女性は休日(残念)、青年は事情を話すと気持よく受け取ってくれた。
これで心置きなくさようならだ、と安堵した。